放射線部門は、九州大学病院のすべての診療科・部門と密接に協力して、放射線に関連す
る検査、画像診断・インターベンショナルラジオロジー、放射線治療、核医学検査および
治療を行っています。
「運営体制」
診断・治療・核医学の3部門に分かれ、医師5名(兼任2名)、診療放射線技師68名、看護師
13名、事務補佐員など10名で運営しています。業務時間外は、診療放射線技師2名勤務し
ています。
「運営方針」
患者さんの負担はできるだけ軽く、短時間に、精密で安全な検査・治療を遂行することを
心がけ、診療科との密接な連携の下に検査・治療を行っています。
診療放射線技師構成
技師長 1名、副技師長 3名、主任技師 15名、技師 68名
胸腹骨撮影グループ
業務概要
1)主なX線検査
胸部・腹部・乳房X線撮影、および全身の骨単純X線撮影。病棟・手術部でのX線撮影
2)X線単純撮影検査の特徴
X線単純撮影検査は、画像検査として、スクリ-ニングや経過観察に用いられます。臓器の形状やガスの分布異常、脊椎や下肢の計
測、骨折や石灰化、関節の動態検査等など器質的疾患の評価に用いられています。
当グループでは、胸腹部撮影および骨撮影、手術部での術前・術中、術後の撮影、手術中のX線透視検査を行っています。中でも骨撮影については多岐にわたる撮影部位に対応できる撮影技術と知識が必要となります。

一般の撮影室

撮影風景
また、小児撮影は小さなお子様が患者となるため、撮影室も子供たちができるだけ緊張しないような工夫をしています。

小児用撮影室①

小児用撮影②
ポータブル撮影装置は放射線部内の撮影室へ来ることができない患者様や隔離状態の方、ICUなどの集中治療室の患者様を撮影するための装置です。最新の撮影装置はFPDと呼ばれる従来のフィルムに代わる装置を用い、撮影した画像を専用の端末で瞬時に画像として確認ができます。ポータブル撮影装置にモニターが組み込まれた一体型のものがあります。

ポータブルX線撮影装置
CTグループ
1.業務概要
1)主な検査部位
頭部、頚部、胸部、心臓、上腹部、肝、膵、腎、骨盤、四肢
2)CT検査の特徴
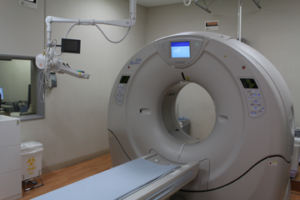
X線CT装置
CTは、Computed Tomography(コンピューター断層撮影)の略称です。X線を利用し、人体の輪切り(横断像)画像を得ます。撮影時間は極めて短く、数秒で全身を撮影することが可能です。体内の様々な病巣を発見することができますが、こまかなもの描出する能力(空間分解能)が高い特長を備えています。
一方で、正常臓器と病変などを分けて表現する能力(組織分解能)は低く、課題となっています。この課題に対しては、造影剤を使用することにより、明瞭に描出します。また、立体的な三次元画像を作成することもできます。
一方で、X線の被ばく線量が多い課題もあります。高精度な検出器や新しい画像処理法などを応用し、適切な線量で検査できるよう努めています。
造影透視グループ
1.業務概要
1)主な検査部位
消化管、胆道、膵臓、腎臓、膀胱
2)透視検査の特徴
透視検査は、X線テレビシステムを利用して人体の透過像を動画で見たり、X線写真を撮影したりします.
造影剤を体内に注入したり,飲んだりする事によって見えづらい体内の臓器の形態,機能などを観察することが出来るようになります。よく知られている透視検査はバリウムを利用した消化管検査があります.バリウムなどの造影剤を使用することにより、他の検査では困難となることが多い粘膜の微細な変化と全体像を把握が同時に可能であり、病態の把握や治療方針の決定に役立ちます。
その他にも透視検査室では透視画像を参照しながら行うファイバー検査、治療や栄養薬剤の投与のためのカテーテル挿入、狭窄部位を広げるステントの挿入などを行っています。

X線テレビシステム

消化管検査(胃)
歯科グループ
1.業務概要
1)主な検査部位
口腔領域、顎顔面領域
2)歯科でのX線撮影について
(1)歯科におけるX線撮影は大きく分けて口内法X線撮影と口外法X線撮影があります。当院において口内法X線撮影では口腔内にイメージングプレートを挿入して歯および歯周組織を撮影します。
(2)また、口外法X線撮影は口内法X線撮影以外の撮影の事をさします。なかでも、歯科ではパノラマX線撮影が特に知られています。パノラマX線撮影は上・下顎骨、歯、顎関節、上顎洞などの顎顔面領域を一度の撮影で広く観察できます。一般の開業歯科医院においても、これらは歯科診療において無くてはならない撮影法となっています。
(3)“安心で安全かつ高度な医療を提供します”を基本方針とし、“正確な画像診断”および“最先端技術の習得”を目標としてグループ全体で診療科と連携を執って診療に従事しています。
血管造影グループ
1.業務概要
1)主な検査部位
頭部,頚部,胸部,心臓,腹部,骨盤,四肢
2)血管造影検査、心臓カテーテル検査の特徴

図1 血管造影撮影装置(Cアーム)
血管造影部門では,鼠径部や手首などからカテーテルという細い管を血管内に挿入し,目的とする血管に造影剤を注入しながらX線撮影を行うことで,腫瘍などの占拠性病変や血管性病変の画像診断を行っています.また診断のみならず,腫瘍への薬物注入や腫瘍を栄養している動脈の塞栓術,事故などで発生した出血に対する動脈塞栓術,狭窄・閉塞した動脈をバルーンやステントを挿入することで血管を再建する血管形成術,腹部大動脈瘤に対するステント留置術など,従来は手術などで治療されていた病変に対して,カテーテル技術を利用した治療(IVR: Interventional Radiology)も盛んに行っています.近年増加している脳卒中に対する血管内治療も積極的に行われており,緊急の症例にも対応しています.

図2 血管造影撮影装置(IVR-CT)
血管造影ではDigital Subtraction Angiography(DSA)という技術を用いて血管の画像のみを表示することができます.血管造影室にはCアーム型血管造影装置が搭載されており,様々な角度から血管を造影し診断を行います(図1).またCアームを回転させながら撮影することで,血管を3次元的に描出することも可能です.さらに,肝細胞がんや肝転移など肝疾患の診断精度向上のために,CTと組み合わせて検査を行うCTAPやCTHAが実施されています(図2).
スタッフが装置の特性を理解し,診断・治療に有用な画像を提供しています.
(2)心臓カテーテル検査
心臓カテーテル検査は,鼠径部や肘,手首などからカテーテルという細い管を血管内に挿入してカテーテル先端を心臓までもっていき,心内血圧測定や酸素飽和度の測定,心拍出量の測定することにより,心機能解析を行うものです.また,造影剤を使用することにより,心臓や動脈,静脈の形態的な検査もしくは,血行動態の診断が可能になります.

図3 心臓カテーテル検査室
特に,近年増加傾向にある狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の患者さんに対しては,冠状動脈造影を実施しています.血管造影同様,IVRも盛んに行われ,虚血性心疾患の患者さんに対しては,風船治療(POBA: plain old balloon angioplasty),ステント留置術,石灰化が強い病変に対してはロータブレーターなどの経皮的冠状動脈形成術(PCI: percutaneous coronary intervention)を行っています.その他にも特殊な治療として,不整脈に対するカテーテルアブレーションや慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する肺動脈拡張術なども行っています.
心臓カテーテル検査室にはCアーム型造影装置が搭載されており,様々な角度から心臓の血管を造影して診断を行います(図3).血管造影と同様に,スタッフが装置の特性を理解し,診断・治療に有用な画像を提供しています.
MRグループ
1.業務概要
1)主な検査部位
頭部、頚部、脊髄、心臓、乳腺、肝臓、膵臓、腎臓、骨盤、四肢
2)MR検査の特徴
MRとは(Magnetic Resonance(Imaging): 磁気共鳴画像診断装置)の略称で、磁気共鳴現象を利用して人体の断層像を得る検査です。
本院では、3.0T(テスラ)の高磁場MR装置を有しており、高精細な画像を取得できます。コントラスト分解能に優れており、様々な部位の検査を行うことができ、特に脳・脊髄系の疾患に有用です。
さらに、脳や心臓など様々な部位において、形態学的な評価のみならず機能的な評価が可能です。
また、造影剤を使用せずに血管の撮影を行うこともできます。放射線を使用しないので、被ばくが無いという利点がありますが、強力な磁場を使用するため、体内に金属があると検査できない場合もあります。

3T-MRI装置

セットアップ風景
超音波グループ
1.業務概要
1)主な検査部位
腹部、頸部、頸動脈、下肢血管、皮下・軟部組織、その他、乳腺及び穿刺(放射線科施行)
2)超音波検査の特徴
超音波検査とは、超音波を利用して人体の断層像を得ることができる検査です。他の放射線検査のよう被曝が無く、簡便に行うことができます。また、生体内の任意の断層像や血流情報など様々な情報を画像化することによって、病気の早期発見や診断、治療方針の決定、治療効果判定、定期的なフォローアップなどの診断に役立てることができます。
放射線治療グループ
1.業務概要
1)主な治療方法
高エネルギーX線・電子線体外照射,術中照射,全身照射,定位放射線治療,強度変調放射線治療,腔内照射(192-Ir),組織内照射(125-I,198-Au)など
2)放射線治療の特徴
放射線治療(radiation therapy or radiotherapy)とは、放射線が持つ電離作用で悪性腫瘍を制御することを目的としています。また、正常な組織へ照射を行い、機能を低下もしくは停止させる目的での照射もあります(免疫抑制など)。
放射線治療には、大きく分けて体の外から放射線をあてる外部照射(体外照射,定位照射など)と、体の中に放射線を出す物質(放射性同位元素)を入れて治療する内部照射(腔内照射,組織内照射など)があります。
近年の、放射線治療はCT画像をもとに治療計画が行われ、治療精度が飛躍的に向上しています。

放射線治療装置
①定位放射線治療とは、極小照射野で病変部に放射線線量を集中させつつ周囲の正常組織に対する放射線線量を極力抑えることにより、副作用を軽減しかつ腫瘍の制御率を上げる治療法です。当院では、主に肺または肝臓がんなどの体幹部の腫瘍に対して体幹部定位放射線治療を行い、手術と同程度の治療成績が得られています。また、脳腫瘍、脳転移腫瘍などに対しても頭部定位照射を行っています。
②強度変調放射線治療(Intensity Modulated Radiation Therapy: IMRT)とは、照射面積内の放射線強度を変更しながら多方向から照射することにより、正常組織には少ない放射線線量を、腫瘍には多くの放射線線量を照射できる方法で、腫瘍制御率の向上や合併症の軽減が期待されています。当院では、各種がんの治療に強度変調放射線治療を行っています。
③画像誘導放射線治療とは、照射直前に取得された画像に基づき、治療計画で決定した照

セットアップ風景
射位置を可能な限り再現してから放射線を照射する方法です。この方法を用いることで、より正確な位置合わせが可能となり、より正常組織の被ばく線量を低減できるようになります。
当院ではこれらの治療方法を用い、また組み合わせて高精度な放射線治療を実施しています。
RIグループ
1.業務概要
1)主な検査内容
(1)画像検査
脳血流、脳神経受容体、脳酸素代謝、全身糖代謝、脳糖代謝、心筋血流、心筋梗塞、心筋交感神経受容体、心筋脂肪酸、腫瘍炎症、骨、骨髄、脳槽、唾液腺、甲状腺、副甲状腺、肺血流、肺換気、肝、肝受容体、胆道、副腎皮質、副腎髄質、腎、メッケル憩室、消化管出血、門脈、センチネルリンパ 等
(2)機能検査
甲状腺摂取率、循環血液量
2)RI検査の特徴
核医学検査はRI(Radio Isotope*:放射性同位元素)検査とも呼ばれているが、微量のRIを、臓器や組織、病変に特異的に集まる薬に標識(分子の一部に組み込む)した放射性医薬品を使って病気の有無、病態などを調べる検査である。目的とする臓器や組織に集まった放射性医薬品は、そこから放射線(ガンマ線)を体外に向けて放出する。その放射線をガンマカメラと呼ばれる専用のカメラを用いて画像にする。この画像から臓器の機能や代謝がどのようになっているかがわかる検査である。
現在、すべての装置にCT装置が搭載されておりRIの画像との重ね合わせ(fusion)を行い、さらに診断精度の向上に役立っている。

PET/CT装置

SPECT‐CT装置
3Dグループ
1.業務概要
1)主な検査部位
心臓、全身の血管、骨など
2)3D画像の特徴
3D(スリー ディ)とは(three dimensions)の略称で、3次元つまり立体の意味です。おもにCT画像を専用のワークステーションというコンピュータを使って、さまざまな方向から見ることができる立体的な画像を作成します。臨床上の需要が高まり、九大病院放射線部では、2012年より3D部署(ラボ)として独立しました。心臓や血管、骨などを実物のように立体的に見ることができるため、解剖学的な形態や位置関係などをわかりやすく表現することができます。3D画像は、手術の計画や学生教育、また患者さんへの説明のためなど幅広く用いられています。